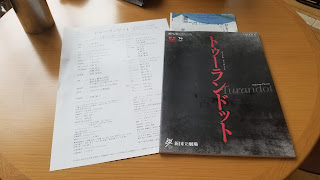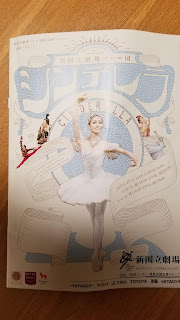槍ヶ岳ワンデイ(日帰り登山へのこだわり)

槍ヶ岳ワンデイ 槍ヶ岳ワンデイGPSログ 弁護士の仕事は裁判所に行ったりクライアントと打ち合わせをしたりといった業務以外に とにかく手間と時間がかかる。 法律を調べたり書面を書いたりする時間だ。 平日は、裁判所の期日、 クライアントとの打ち合わせ、 その他日常的な庶務雑事で忙殺されるため、 まとまった時間はなかなか取れない。 そうすると しっかりと調べ考え書く業務というのは、 まとまった時間の取れる 休日にやるほかない。 休日2日とも山に使ってしまっては、その週は調べ考え書くための時間がなくなってしまう。 さらに家族の時間もしっかり取りたい。 子どもたちをいろんなところに連れて行ってあげたい。 そうすると、山はいかに日帰りで完結させるかが重要な課題となる。 今回も金曜日の19時まで仕事をして 20時出発、 弁護士の友人と新穂高まで 車を走らせ、 車中で仮眠をした後、 午前3時半起床午前4時出発。 その後はGPSログのとおり13時間30分の山行。 槍ヶ岳は、30km弱の行程、2000m以上の標高差、どこまでも美しい景色と、ワンデイで完全燃焼できる最高の山だ。